| |
3ヵ月 |
6ヵ月 |
9ヵ月 |
12ヵ月 |
看
護
実
践
力 |
■指導を受けながら、患者の気持ちを配慮して、安全安楽な日常生活上の援助ができる
■助言を受けながら、担当患者への援助の意味・効果を考えて、評価できる
■助言を受けながら、担当患者への援助内容を記録できる |
■助言を受けながら、担当患者のその日の問題を明確にし、それに沿った看護を実践できる
■助言を受けながら、担当患者の看護過程に沿った看護記録が書ける
■助言を受けながら、担当患者の状態に合わせて、安全・安楽な援助を工夫できる |
■受け持ち患者の病態生理・治療方針がわかり、意図的に情報収集し、指導を受けながら看護計画を立案・実施・評価できる
■受け持ち患者の看護過程に沿った、看護記録が書ける
■受け持ち患者の看護方針をチームメンバーに伝達し、ケアの継続をアピールできる
■看護基準やアセスメントツールを活用して受け持ち患者の状態をアセスメントし、ケア計画・実施に活用できる |
■受け持ち患者の全体像・その時々の状況を把握し、助言を受けながら必要な看護を判断・実施・評価し、次の看護に活かすことができる
■受け持ち患者の個別性をふまえた、患者・家族への生活指導ができる |
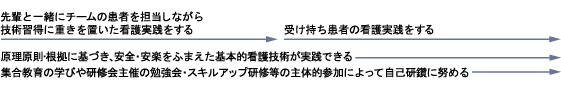 |
| 基本看護技術 |
生命徴候の変化を観察・アセスメント・報告ができる |
生命を守り、回復を助ける援助ができる |
■バイタルサインの測定・評価・報告
■BG測定・評価・報告
■感染予防技術
■安全確保技術
■与薬の技術
(内服管理・輸液準備)
■日常生活援助技術 |
■症状・生体機能管理技術
■呼吸・循環を整える技術
■与薬の技術
(輸液管理・インスリン)
■安全管理の技術
■コミュニケーション技術 |
■創傷管理技術
■与薬の技術
(輸血・抗癌剤・麻薬・毒薬・劇薬)
■救急救命処置技術
(気道確保・ 救急カート) |
■救急救命処置技術
(挿管・呼吸器準備と管理)
■死後の処置
■1年を振り返り、不足している技術を強化する |
組
織
人
と
し
て
の
行
動 |
■病院・看護部の理念、目標を知る
■職場内のルールを知る
■患者のプライバシーを守る
■清潔感のある身だしなみを整える
■挨拶ができる
■報告・連絡・相談ができる
■困ったときに、プリセプターに相談できる
■自分の健康管理ができる |
■チームメンバーと情報を共有し、指示受け・報告をしながら行動し、夜勤の一人立ちができる
■カンファレンスやミーティングで、自分の意見を自ら言うことができる
■適切な言葉づかいで、同僚や医師とコミュニケーションをとることができる
■困ったときに、プリセプターや先輩の協力を、自ら求めることができる |
■まわりの状況に目を向けられ、他のスタッフと協力し合うことができる |
■病院・職場のルールを守り、看護チームの一員として、責任ある行動がとれる |
管
理 |
■自分の勤務場所の特殊性を知る
■病院内の構造やシステム・他部門との連携ルール
■各種伝票の取り扱いを知る(SPD・ME・薬剤部など)
■パソコン操作ができる
■スタンダードプリコーションを知り、活用できる
■患者の安全に気を配り、危険防止のための行動ができる(誤認防止・転倒転落防止・病棟の整理整頓・後片づけ) |
■院内ルール・システムを活用できる(搬送・外来システムなど)
■事故発生時はリーダーナースに報告し、適切な対応ができる
■針事故時の対応を知り、感染予防対応と報告ができる |
■夜勤の院内管理体制を知り、活用できる
(夜勤師長への報告・ME・滅菌物の連絡・受け取り)
■備品・設備の不備や不足に気づき、責任者に報告できる |
■患者の安全に気を配り、積極的に事故防止に努めることができる |
|
教
育
・
研
究 |
■院内教育プログラム・部署別オリエンテーション
■技術訓練指導に意欲的に参加し、専門知識・技術を修得していくことができる |
■スキルアップ研修等に主体的に参加することができる |
■看護研究発表の場やリスクシンポジウム等に、関心を持って参加することができる |
■各部署の勉強会で、割り当てられた課題について学習し、発表することができる
■2年目に向けて、自己の看護実践力を評価し、課題を明らかにすることができる |
*担当患者への援助を通し、患者の気持ちを配慮した
看護の学びを、レポートする |
|
*受け持ち患者の看護実践評価を、レポートする |
![]()
